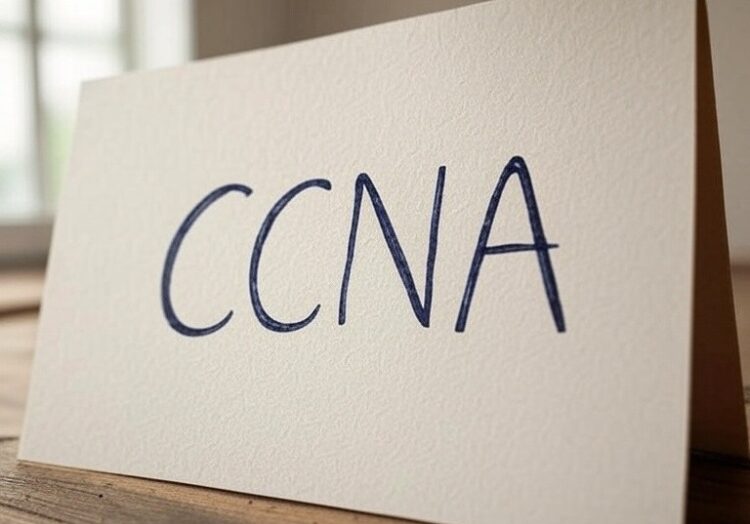
NW実務ほぼ未経験からCCNA資格を取得した話(試験対策紹介その2)
こんにちは。NWほぼ初心者のインフラエンジニアのおじさんです。
前回の記事に引き続き、今回もNW実務ほぼ未経験の私がCCNAを取得した際の試験対策を紹介します。
1記事にまとめるとボリュームが大きくなりますので、以下の2回に分けて投稿しております。今回は後編です。
(1)筆者とCCNAの基本的な情報共有
(2)試験対策・学習方法の紹介(←今回はこちら)
今回は具体的な試験対策を紹介します。
学習教材
以下を利用して学習に取り組みました。
- テキスト
シスコ技術者認定教科書 CCNA 完全合格テキスト&問題集
いわゆる「白本」と呼ばれるテキストです。全800ページほどあり大ボリュームです。
最近、最新の試験内容に合わせた改訂版が発売されました。
私は4月から学習開始しましたので、改定前のテキストを利用しました。
- 問題集
Ping-t
web問題集です。CCNAについては特に手厚く、1000問程の問題やシミュレーション問題もカバーされています。
基本無料で、アカウント登録で1部の問題を解くことができます。有料プランに登録することですべての問題を利用可能です。
有料プランは月単位で登録が可能です。
- 学習環境
Cisco Packet Tracer
Cisco公式が提供するネットワークシミュレーションソフトウェアです。(無料で利用可能です)
ネットワーク構成、トラブルシューティング、プロトコルの動作をシミュレーションできます。
PCにソフトをインストールするだけでルータやスイッチのコマンド学習が可能です。
学習方法

- 学習期間:3か月半
- 1日の学習時間:1~2時間
ただ、想像していたよりもボリュームが多く、3か月経過時点で体感的に合格ラインには到達出来ていなかったため、やむをえず半月延長しています・・・
- スケジュール
スケジュールごとの学習内容は以下の通りです。
| 時期 | 学習内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 0か月 | 2か月 |
|
| 2 | 2か月 | 3か月半 |
|
| 3 | 試験 前日 |
|
試験当日

ピアソンビューからで試験予約を行ったテストセンターに向かい、受験しました。
受験時は以下の点に注意が必要です。
- 制限時間
- 試験には制限時間(120分)があります。
- 問題
試験結果
無事に合格出来ました!
スコアは以下の通りです。
| 項目 | 正答率 |
|---|---|
| Automation and Programmability | 70% |
| Network Access | 45% |
| IP Connectivity | 92% |
| IP Services | 70% |
| Security Fundamentals | 80% |
| Network Fundamentals | 70% |
私は「Network Access」の得点がいまひとつだったようです。
試験結果の振り返り
- 試験時間が足りなかった。
最終問題まで到達する頃には終了時間ギリギリでした。
- パーセンテージが低い「Network Access」に関しては、恐らく時間の都合で全てスキップした「シミュレーション問題」のカテゴリかと思います。
私が出題されたのは簡単なルーティング問題ですので、十分な時間を確保できていれば、もっと正答率を上げられたかと思います。
なお、試験会場では完了後すぐに試験結果が書かれた書類を頂きます。
本来はその場で合否がわかるはずですが、私の場合は「Pending(保留)」表示でした。
その後1時間以内にピアソンビューから試験結果の通知メールが届き、ピアソンビューにログインして合否を確認出来ました。
CCNA学習方法のまとめ
- 無知識から合格レベルまで知識の定着を目指すなら問題集(Ping-t)がオススメ
無料版では問題数に制限があるため有料プランを推奨
なお、問題数は1000問以上ありますので、スケジュール的にもある程度の取捨選択が必要です。
私は「ピックアップ問題」を重点的に行い、それ以外の問題は1度解くのみにしました。
- 白本は全体の知識の振り返りとして利用
私の場合は、書籍の読み込みのみでは知識の定着は出来ませんでしたので、問題集で一通りの理解をした後に白本を読み込むことで、より内容の理解が深まりました。
- 実機も触る
シミュレーション問題も出題されますので、Cisco Packet Tracerや実機ルータ、スイッチを使ったコマンド操作にも慣れておく必要があります。
さいごに
業務をしながらCCNAの勉強をするのは非常にストレスがかかりましたが、これまでよくわかっていなかったNW領域の基本に触れることができましたので、今後十分実務で役立つ知識を得られたと感じています。
今後もさらにエンジニアとしての対応範囲を広げるため、新たな知識の習得にトライしていきたいですね。
今回の記事がこれからCCNAを受験する方の参考となるよう祈っております!
ここまでご覧頂きありがとうございました!
